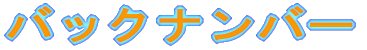|
![]()
2020年3月1日(日) 四旬節第1主日 マタイによる福音書4章1節-11節
イエスはその運動に参加者を集め、どう生きるかを山上で語られた。モーセが出エジプトしたヘブライの民に神の言葉を語ったように。今日の箇所では、イエスが運動を始める前に、運動の方法論を決めたことが物語形式で表されている。著者は、イエスが十字架刑死後、原始キリスト教団が「神の子」と呼ばれたことから、イエスの生涯を振り返ったのであろう。 さて、「荒れ野」の旅で、試みる者に対抗したイエスの拠り所は、堅さ、確かさ、岩、アーメンと呼ばれる「神」への深い信頼だ。これまた、出エジプトし荒野を旅するヘブライの民が頼ったモーセを仲介した神の言葉であったように。「だれもが大事にされる」荒れ野の旅に教会も神の言葉を深く学び、従って行こう。 |
2020年3月8日(日) 四旬節第2主日 マタイによる福音書17章1節-9節
イエスはいわゆる、『荒野の誘惑』物語において「神の国」運動の方針を定めた。つまり、世界が期待する「神の子性」の放棄、超人ではなく、神の言葉に堅く立ち、唯一の拠り所、指標として従うことを選んだ。 しかし、イエスに呼ばれて運動に参加した弟子たちは、この世の価値観に縛られ、イエスをこの世の王、権力者、奇跡行為者と見なし、その恩恵に与ろうとしていたイエスの苦難の道を拒否した。イエスはペトロに言った。「サタンよ、引き下がれ」と。福音書を読んで来て、誘惑に弱い弟子たちへと同様、あらためて、神の言葉に忠実であるイエスの道を行けと勧められた。 |
2020年3月15日(日) 四旬節第3主日 ヨハネによる福音書4章5節-42節
イエスの「神の国」運動は、「石をパンに変えない」ことを方針として始まった。つまり、物質に過度の依存をしないことだ。なぜなら、「神のことば」によって生きるとは、物質に対しては必要な分だけの賢明なコントロールすることだと、『出エジプトのマナの逸話』は教えている。 ガリラヤの貧しい人たちは極度に飢えていた。そんな彼らの第一の救いは、まず、毎日食べられることだ。にもかかわらず、イエスがパンだけで人は生きるものではない、と精神論の説教をしただろうか。現に、イエスはその運動の合言葉を弟子たちに教えたが、それには「日毎のパンが与えられるように」とある。しかし、イエスがガリラヤの人たちに食糧配給し続けるには、それこそ、試みる者に頭を下げて全世界の富を分けて貰うしかないだろう。だから、神だけに従うイエスは「パンのみ」による救済をしなかった。イエスはパンが公平に分配される神の心の貫徹する状態にしたかった。 それには、持っている者の良心に訴える、例えば、軍拡競争ではなく環境保全へと。すなわち、回心、神に従うことへと呼びかけ社会変革に進むしかなかった。けれど、それを座して待つだけでは、『ラザロと金持ち』の寓話のように餓死者は増える一方だ。だから、まず、イエスと弟子たちは自らも足りないパンを分け与え、エルサレムの支配者に訴えの旅に出たのであった。イエスたちにはジレンマだったろう。試みる者の「神の子なら」の誘いに揺らいだであろう。キリスト者は全知全能の神への信仰を考えなおさなければならない。 同じく、今日のサマリアの井戸の物語では女性の水汲み労働の過酷さへのイエスの同情は水汲みの軽減をしてやりたかったのではないか。とっさに、「生きた水を与えよう」と口からでたのは女性故に課せられた家事労働に縛られ、奴隷のように働かされ、不自由を強いられた女性への深い共感だった。彼女の汲む水は汗と涙からの苦い水だ。イエスはそれを生きた清水、命を与える水にかえたかったのだ。もちろん、イエスにそんな力はなく、水の供給はできない、ただ、神の言葉の供給しかない。では、女性の重労働を軽減するには、女性を不平等にする社会の仕組みを見て、神の思いの実現へと変えなければならない。「霊と心理の礼拝」とは、神の思いが天に行われるように地にも行われる、ことだ。パンや水が公平に分配され、だれもが置き去りにされない状態へみんなで変換して行く過程がイエスの運動なのだ。 |
2020年3月22日(日) 四旬節第4主日 ヨハネによる福音書9章1-41節
この世界は弱肉強食だ。強い者・富める者が優遇される社会となっている。イエス時代のユダヤでは強者富者がユダヤ教指導者であり、弱者、即ち、貧者、病者、外国人は「罪人」と呼ばれ、差別・搾取が宗教的に正当化されていた。そのため、後者は極度な苦難のなかに生きていた。 悲惨なガリラヤの人々にこころ痛めたイエスはヤーウエ神の思いに立ち返り、「誰もが大事にされる」神の国運動を始めた。その際、イエスは「強者」ではなく神の言葉だけを頼りにする「こころ貧しい者」となることを運動方針とした。飢えた人たちには、必要なパンが与えられるよう、ユダヤ教指導者に「神の言葉」に戻るよう呼びかけた。 サマリアではユダヤ人からの差別や重労働で疲労困憊していた女性の荷(苦い水)を軽くしようと永遠の命、つまり、「いつも明るく生き生きとする力『生きた水』」に変えることに立ち上がり、社会、男性の変革を汲む提案した。エルサレムでは、イエスの出会った目の見えないため乞食としか生きられない男を立ち上がらせるために、彼を押しつぶしているユダヤ教指導者の目を覚まそうとした。 しかし、指導者たちの頑迷固陋は一層深まり、逆に、イエスを神を冒涜する者とし迫害し始めた。元来、ユダヤの先祖たちは奴隷であったにもかかわらず、神ヤーウエが目を掛けられた(言葉を与えられた)故に、立ち上がり、今の恵まれた境遇を得たことを忘れ、他者を奴隷にしてしまった。その神への背反をイエスは指摘したのに。 |
2020年3月29日(日) 四旬節第5主日 ヨハネによる福音書11章1-45節
人生は四苦だ、と言ったのはお釈迦さまだ。それは、聖書の世界でも同じ、詩編23のように「死の陰を歩む」のが人生、だから、神のことばに従って行くよう招いている。さて、イエスの出会った人々はそれぞれ重荷を負わされ、苦難に喘いでいた。イエスはこころ痛め、寄り添った。 今日の箇所では、人の「死」に直面した苦しみだ。人には「死」の限界があることは当たり前だ、しかし、それを受け入れることは容易ではない。だからこそ、人は「不老不死」を手に入れようと奔走する。宗教にすがることもその一つだ。旧約聖書には来世の言及はない、ただし、ギリシャ思想の「霊魂不滅」観の影響後、復活思想が生まれ知恵文学や黙示文学には表れて来た。イエス時代には終わりの日の復活への信仰は浸透していた。マリアやマルタのイエスへの期待は「神の子」イエスであるなら、ラザロを死なせなかったはず、と言うことから分かる。けれど、イエスはそんな「蘇生」と言う通俗的迷信に応えるであろうか。もちろん、姉妹の弟喪失への悲しみに寄り添いたいと思っただろうが、「蘇らせる」との姉妹の安易な願望に答えたのか。 人は必ず死に、愛する人と別れねばならないとの「苦しみ」をどう受け留めるのが大問題なのだけれど、姉妹の死の苦しみへの寄り添いを「蘇生」にしては安直過ぎると言えまいか。まさに、「石をパンに変えろ」の誘惑に負けたのではないか。残念ながら、今日の箇所を読む限りは「そうだ。」としか言えない。ヨハネ福音書の著者は、そんな通俗的なイエスを書いて、読む者に信じろと言っているのか。それでは、彼の福音執筆の目的である「見ないで信じる者は幸い」に矛盾する。ヨハネ福音書の著者も、「死」に直面した人との寄り添いには混乱している。 |
|
|